毎年春、美しいピンク色で日本列島を彩りながら北上する桜。桜の花見といえば、満開の花を鑑賞したり、樹の下で宴会をしたりというイメージが浮かぶと思いますが、歴史は意外と古く、その起源は今から約1300年前の奈良時代にまで遡ります。今回の特集では、古来から日本の春の楽しみとして親しまれている花見の歴史や、実は多様な桜の種類などを紐解いてみたいと思います。
お花見の歴史
さくらの「さ」は山の神(田の神)、「くら」は神さまの座るところを意味するといわれ、本来の花見は、祓いのための宗教行事だったと考えられています。桜の開花は山の神が桜の木を依代として降りて来た合図とされ、その木の下で神様に料理とお酒を備え、人間も一緒に食事をしながら春の訪れに感謝するという意味があったようです。
奈良〜平安時代(710〜1185) ―梅の花見から桜の花見へ―
奈良時代、貴族の間では、その頃中国から伝わったばかりの梅を鑑賞する花見の習慣がありました。平安時代に入り、日本独自の国風文化が盛んになるとともに、花見で鑑賞する花は徐々に桜へ変わっていきました。 飛鳥時代から奈良時代に編纂された『万葉集』では、桜を詠んだ歌が43首、梅を詠んだ歌が約110首が収められていますが、平安時代に編纂された『古今和歌集』では、桜の歌が70首、梅の歌が18首と首位交代しています。
【日本最古の花見の宴】
日本最古の花見の記録は、平安時代初期の勅撰史書『日本後紀』に見られる「812年3月、嵯峨天皇が神泉苑で花宴の節を催した」という旨の記述です。同時期に編纂された漢詩集『凌雲集』には、同じ花宴の節で嵯峨天皇が詠んだ「神泉苑花宴賦落花篇」という題の漢詩が収められています。花宴の節の前年から毎年、地主神社の桜が天皇に献上されていることから、この花宴で鑑賞された花は桜だったと言われています。その後、貴族の間で桜の花見の習慣が広まり、現代へ続く花見の起源になりました。
【天皇主催の恒例行事に】
831年から、桜の花見は宮中で天皇が主催する恒例の行事となりました。また、貴族の家の庭に桜の木が植えられるようになり、『作庭記』には「庭には花(桜)の木を植えるべし」と記されています。現代も花見の名所となっている京都市東山エリアの桜も、この頃に植えられたと言われています。
【源氏物語の花宴】
『源氏物語』第八帖「花宴」には、宮中の紫宸殿で開催された花見の様子が描かれています。帝や中宮、その他大勢の貴族たちが集う中、二十歳の光源氏が、漢詩を詠んだり、「春の鶯がさえずる」という舞を披露したりします。宴は日が落ちても続き、夜更けの月が高くなった頃にやっと果てました。人々が解散し静まり返った宮中で、光源氏が朧月夜に出逢うシーンが描かれています。
鎌倉・室町時代(1185〜1573) ―武士階級にも広まった花見の風習―
吉田兼好の随筆集『徒然草』(1330年頃)第137段には、京都の人々の花見と「片田舎の人々」の花見の楽しみ方の違いが記されています。片田舎の人々が風流を装ったり、騒がしく祝宴を行ったりすることに対して批判めいた表現がされていますが、このことから、徒然草が記された頃には、地方でも花見の宴が催されていたことがうかがえます。
安土桃山時代(1573〜1603) ―花見をしに山野へ外出―
この時代、貴族や武士たちは家の庭や敷地内だけでなく、外へ出かけて花見をするようになりました。1594年、豊臣秀吉は、徳川家康、伊達政宗、前田利家などを引き連れ、吉野山で大規模な花見の宴「吉野の花見」を催しました。この時の一行の人数は5000人に及んだといいます。また、1598年、秀吉が晩年に醍醐寺三宝院裏の山麓で催した「醍醐の花見」には約1300人が参加したと言われています。

江戸時代(1603〜1868) ―庶民も花見を楽しみ、桜の品種改良が盛んに―
【江戸時代も桜の名所だった上野公園】
江戸時代、花見の習慣は庶民にも広まっていきました。この時代、江戸で最も有名だった花見の名所は、今も名所となっている上野公園で、当時は忍岡(しのぶがおか)と呼ばれていました。1625年(寛永2年)、津藩藤堂家の下屋敷があった忍岡に寛永寺が建立され、初代住職の天海は、寺の境内に京都の吉野山の山桜の苗木を移植しました。その山桜がうまく開花した1660年頃から、寛永寺は美しい山桜で有名なスポットとなり、元禄期(1688〜1704)には桜の名所として定着しました。
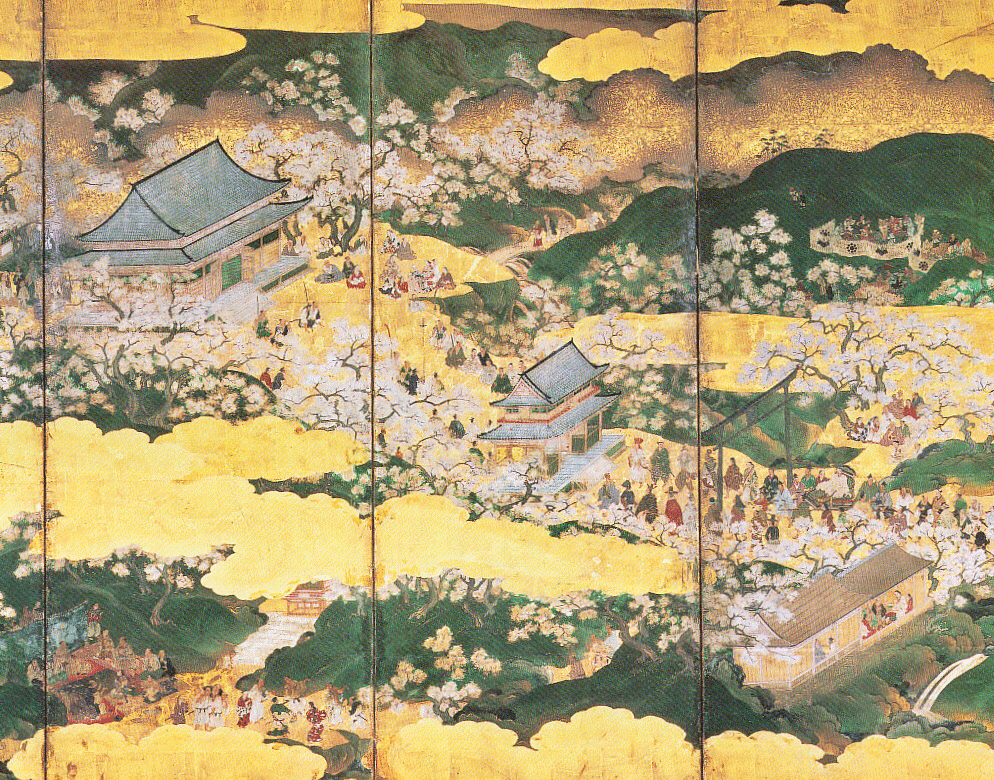
【俳句や行楽ガイドにも取り上げられた寛永寺の桜】
松尾芭蕉は寛永寺の桜について「花の雲鐘は上野か浅草か」と俳句に詠んでいます。また、江戸時代の年中行事ガイド『東都歳時記』(1803〜1838)には当山の桜は、その昔、台命(将軍の命令)によりて吉野の苗を植えさせられし所とぞ、盛りのころは貴賎雅俗ここに群り、花下に遊宴して、夕照の斜なるを惜しむ」と、行楽ガイド『江戸名所花暦』(1827)には「東都第一の花の名所にて、彼岸桜より咲き出でて一重八重追々咲き続き、弥生の末まで花のたゆることなし」と記されています。
【小袖幕を張り巡らせ、毛氈を敷いて楽しむ宴】
江戸時代の庶民の花見は、羽織小袖などを木陰に並べ掛けて「小袖幕」を張り巡らせ、その中に毛氈を敷いて座り、酒を飲んだり花見弁当を食べたりなどして楽しむというものでした。歌人の戸田茂睡が記した仮名草子『紫の一本(ひともと)』(1681年頃)には、寛永寺に集った人々が花見に興じる様子が次のように描写されています。 「幕の多きは300余りあり。少なき時は200余りあり。このほかにつれだちたる女房の上着の小袖、男の羽織を、弁当かかげたる細引きにとほして桜の気にゆひつけて、かりの幕にして、毛氈・花むしろしきて酒のむなり。鳴物はならず。小唄・浄瑠璃・踊り・仕舞はとがむることなし」
【音曲は禁止】
寛永寺は、徳川家光が創立した将軍家の菩提寺でした。そのため、花見の際は鳴り物などの音曲が禁じられていました。また閉門は、暮六つ(午後6時頃)で、その時間になると「山同心」という寛永寺の警備員たちが出てきて、花見をしていた人々を退去させました。その際の情景が「千金の時分 追い出す花の山」という川柳に詠まれています。
【桜の新名所、飛鳥山と隅田川堤】
1720年、徳川吉宗は、王子の飛鳥山や浅草の隅田川堤に桜を植え、桜の新名所として庶民を誘致しました。その理由の一つに、庶民たちを寛永寺から遠ざけるためということがありました。またこの頃、「生類憐みの令」で一時的に中止されていた鷹狩りが復活したのですが、鷹場に近い田畑が人々に踏み荒らされるという被害が出てしまいました。そこで、農民たちの収入源となるよう、鷹場に桜の木を植えて新名所にし、花見客を誘致しました。これが、今も名所となっている飛鳥山の桜の始まりです。

明治時代以降(1868〜) ―全国に広まった荒川堤の桜―
明治時代に入ると、日清戦争、日露戦争が起こり、貴族の庭園や武家屋敷は次々と取り壊され、植えられていた桜も焚き木などの燃料にされてしまいました。これにより、江戸時代に改良された多くの種類の桜が激減したものの、駒込の植木職人だった高木孫右衛門が、84種の桜を集めて自宅の庭に移植し保存しました。1886年に孫右衛門が助言しながら造られた荒川堤の桜並木は、1910年頃に花見の新名所として定着しました。78種の桜が植えられた荒川の桜は、各地の研究施設に移植されて品種の保存が行なわれました。これが全国へ広がり、今に至ります。また、1912年には、日米友好の証として荒川の桜の苗木3000本がワシントンに贈られ、ポトマック川の河畔に植えられました。

