『和名類聚抄』
日本の手ぬぐいの原型となった平織りの布片は、約1300年前の奈良時代から使われていました。平安時代中期の辞書『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には「太乃己比(たのごひ)」、末期に成立した説話集『今昔物語集』には「手布(たのごい)」という言葉が見られ、共に手ぬぐいのことを指しています。昔の手ぬぐいも長方形で、縦の長さは3〜9尺(約36〜107cm)といろいろなサイズがあったようです。江戸時代以降、現在のサイズ(約90×35cm)に統一されたと言われています。 今回の特集では、繊維、布の歴史を皮切りに、手ぬぐいの由来、色や柄、さまざまな使い方などをご紹介しましょう。
繊維と布の起源
古代から日本にある繊維には、麻、絹、科(シナ)、楮(コウゾ)、芭蕉(バショウ)、楡(ニレ)、藤(フジ)、葛(クズ)などの内皮の繊維を利用したものがあります。現在も使われている麻の一種「苧麻(チョマ)」の原産地は、東南アジア、東アジア、南アジアです。日本には、縄文時代、朝鮮半島に住んでいた人々が日本へ移住して来た際、彼らの持ち物として持ち込まれたと言われています。また、絹を作る養蚕は、紀元前3000年頃の中国で始まり、弥生時代前期(紀元前300年頃)に中国から朝鮮半島を経て、稲作と同時に日本へ伝わりました。中国の歴史書『三国志』の中の「魏志倭人伝」には、「日本でも麻の栽培や養蚕で繊維を採り、織物を織っている」と記されています。


出典:「帯広百年記念館」http://www.octv.ne.jp/~hyakunen/joumondoki
-gallery.html


出典:Wikipedia
古墳時代
283年、秦の始皇帝の末裔、融通王が、中国の秦民を連れて日本に帰化しました。また、百済の昭古王が絹の織工人を日本へ遣わすなどしたことで、日本の織物の技術は飛躍的に高まりました。5世紀末頃、朝廷は、渡来した百済の職工人の孫に絹や麻の服などを織らせ、手本として地方の工人に送りました。こうして、織物技術が徐々に向上していった時代でした。当時、庶民は日本在来種の植物繊維や麻の布製の簡易服を、貴族は絹の着物をまとっていました。
飛鳥時代
この時代、成年男子には「租庸調」の現物税が課せられ、「調」として麻や綿、粗い絹で織った布の貢納が義務付けられていました。朝廷には織部司(おりべのつかさ)が置かれ、皇族、貴族、僧の服を仕立てるため、目を細かく織った固い絹織物が織られました。また、地方の織物技術の向上を図るため、織部司の文様織りを担う挑文師(あやのし)が地方に派遣されていました。京の都の市には、羅や紗など、さまざまな織り方の布を扱う業者が出始めました。
奈良時代
奈良時代の布は、麻や絹が主流でした。当時、綿(木綿) はほとんど中国から輸入されていたため、綿織物は特に高価なものとして珍重されていました。綿の布は、仏像、神社の装飾品などの掃除に使われていました。
平安時代
892年に菅原道真が記した勅撰史書『類聚国史』には、799年、現在の愛知県の海岸にインド人の船が漂着し、彼らが綿の種を日本に伝えたということが記されています。一方で、神事の際に祭礼を司る人が装身具として手ぬぐい状の綿織物を身につけるなど、布、特に綿はまだ貴重品として扱われていました。
鎌倉時代
麻布が庶民の間で一般的なものになり、手ぬぐいも少しずつ普及し始めました。京都の市には、大舎人織手座、練貫座、小袖座、帯座、絹座、糸座などが出て、織物の専門化、分業化が構築されつつありました。1229年、京都の織物職人たちは、中国から渡来した織物の1つ「唐綾(からあや)」の中国人技術者が逗留していた堺を訪れ、技術を学びました。その後、京都では唐綾が多く織られるようになりました。

室町時代
この時代、手拭いは、水浴びや湯浴みの際、体を洗ったり拭ったりするために使われていました。また、「山繭」の絹に代わり、現在も使われている蚕の絹が中国から大量に輸入されるようになり、戦国大名たちは競って身につけていたようです。周防(現在の山口県)の大内氏は、京都から絹織職人を召喚して絹織物を生産していました。しかしこれは例外的で、一般には中国や朝鮮半島から輸入された絹と綿が使われていました。また、日本の気候風土での栽培に適した綿の種が朝鮮半島から渡来し、綿織物の国内生産が活発になりました。庶民の着物にも、麻や在来種の植物繊維に加えて綿が使われるようになりました。
安土桃山時代
中国や朝鮮半島からの生糸、絹織物、綿の輸入量がさらに増加しました。それに伴い、綿の手ぬぐいが庶民に浸透し、一般的に使われるようになりました。
江戸時代
【手ぬぐいは庶民の生活必需品】
この時代、都市部近郊に綿花の穀倉地帯が発展し、綿の織物とともに普及していきました。1642年、贅沢を禁止し、倹約を推奨する奢侈禁止令(しゃしきんしれい)が出されると、庶民が絹を身に付けることが禁止されました。その代わりに綿の着物が一般的になり、その端切れから手ぬぐいが作られるようになりました。こうして手ぬぐいは庶民の生活必需品となり、現在のタオルのように使われるようになりました。この頃から「手拭」と呼ばれるようになり、入浴に使う手ぬぐいは「湯手(ゆて)」とも呼ばれていました。元禄期(1688~1703)に入ると、日本国内で綿花の重要量をほぼ100%賄えるようになりました。

【古典芸能の舞台にも登場】
手ぬぐいは、日本舞踊や落語の小道具としても使われるようになりました。歌舞伎でも被りものや衣装として登場しました。この頃の庶民は、手拭いの被り方を職種や役割によって変えており、呼び名のない被り方には、よく歌舞伎に由来した名がつけられました。

明治時代
明治時代、大阪で、布に染料を注いで染める「注染(ちゅうせん)」という染色の技術が生まれました。注染では、1回に20〜30枚を、従来よりも複雑な図柄に染めることができました。この頃から発展していった繊維産業とともに、注染の技術は日本中に広まっていきました。しかし、文明開化で日本に西洋のものが多く入ってくるようになり「西洋のものは流行最先端で、日本のものは時代遅れ」といった風潮が高まりました。手ぬぐいもタオルやハンカチなどにとって代わられ、江戸時代ほどには使われなくなりました。

現代
明治時代以降、手ぬぐいは生活必需品という立ち位置ではなくなりました。しかし、感謝の気持ちや特別な時に手ぬぐいを贈るという古来からの慣習は受け継がれ、お店やデパートの贈答品、イベントの記念品などとして需要がありました。2000年代、若者を中心に「和ブーム」が起こると、手ぬぐいの長所や趣が見直され、にわかに注目されるようになりました。さまざまな柄の手拭が小物店や土産店に置かれるようになり、江戸時代の「折り手拭」を応用してティッシュカバーや財布を折って使うなどの実用的なアイデアも次々と生ました。また、スカーフのように首に巻いたり、カバンの取っ手に結んだりと、おしゃれな小間物としても復活しました。

出典:「きものひろば3代目」 http://d.hatena.ne.jp
手ぬぐいの色、柄いろいろ
青系の地色が定番の柄
かまわぬ
「構わぬ」が鎌の絵、◯の記号とひらがなで表された柄です。江戸時代の歌舞伎役者、七代目市川團十郎(1791〜1859)が舞台衣装にこの柄を使いました。
良き事聞く
江戸時代の歌舞伎役者、三代目尾上菊五郎(1784〜1849)が図案を考え、「羽の禿」の衣装に使った柄です。「良き」は、「よき」とも読む「斧」の絵、「事」は「琴」の絵、「聞く」は菊の絵で表されています。
青海波
雅楽の演目の名前で、舞う人の装束に使われます。この吉祥文様には「波のように限りなく広がる」という意味があります。

蜻蛉(とんぼ)
蜻蛉は後ろ向きに飛べないため、「勝ち虫」と呼ばれています。戦国時代の武将が好んで用いた柄です。
麻の葉
模様が麻の葉に似ていることが名前の由来です。成長が早く、高く真っ直ぐに伸びる麻の縁を担いで、赤ん坊の産着などに使われました。
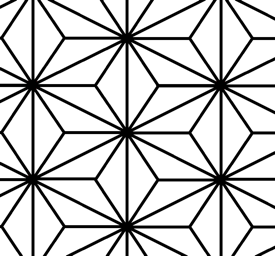
黄系の地色が定番の柄
吉原つなぎ
江戸時代の遊郭街「吉原」が名前の由来です。四角形の四隅を少し内側にへこませた形が隅入り角で、隈入り角を子持ちにし、斜めにつないだ形が並んでいます。江戸〜大正時代、若い男性の半天や浴衣、手ぬぐいなどに使われました。
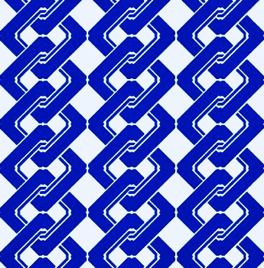
鈴音
鈴が出す「涼やかな音」が、鈴の語源と言われています。鈴は、邪気を払い、魔を除けると考えられていました。
亀甲つなぎ
平安時代から使われている模様です。六角形が隙間なく並んでいるのが亀の甲羅に例えられ、長寿、吉兆などおめでたいことを象徴しています。
白系の地色が定番の柄
ふぐ
昔、ふぐは「ふく」と呼ばれ、福に通じるとされていました。
金魚
金魚は幸福と豊かさの象徴です。中国語では「魚」と「余」が同じ読みのため、「金余」と書いて「お金が余る」という意味にもなります。
ふくろう
ふくろうは「不苦労」、苦労をしないに通じ、縁起かつぎの柄とされています。
蝙蝠(こうもり)
蝙蝠の「蝠」の字は「ふく」と音読みされるため、「福」に通じるとされています。また、蝙蝠は長生きすると考えられていたため、古くは吉祥文様として取り入れられていました。 ※実際の蝙蝠の寿命は3〜20年。種類によって異なる。
遊び犬張子
張り子の犬は、子供の顔に似せて作られ、お宮参りの際に子供の厄除けを祈願して奉納されていました。また、子供の枕元に張り子の人形を置き、お守りにするという習慣もありました。
狸ちらし
「たぬき」は「他抜」、「他を抜く」に通じ、ほかの人を追い抜くという意味があります。
瓢箪(ひょうたん)
実が鈴なりに生ることから「商売繁盛」、種が多いことから「子孫繁栄」、瓢箪が6つ描かれている場合は「無病」が表されています。
菊
昔、菊は延命長寿の薬とされていたことから、「不老不死」や「邪気払い」などの意味が表されています。
露芝
露が乗った草の葉を模様にしたものです。露の重みで草が半分倒れ、乱れている様子は、儚いけれども趣のある様を表しています。
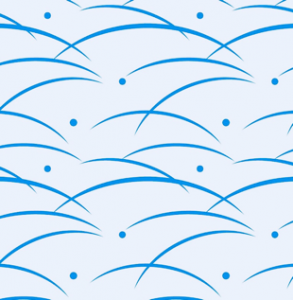
矢絣(やがすり)
飛ばした矢は戻ってこないので、結婚する女性の縁起物の柄として、また「的に当たる」にかけて、家紋やお店の看板などにも使われます。
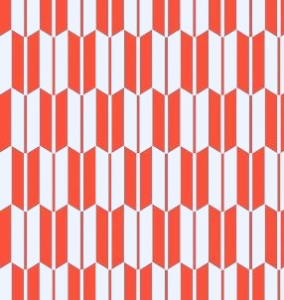
市松
江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松が衣装の袴に用いた文様です。当時の女性の小袖の柄として大流行しました。
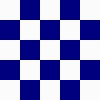
豆知識 手ぬぐいが切りっぱなしなのはなぜ?
手ぬぐいは、濡らして使った後の乾きを早め、汚れを端に溜まりにくくするため両端が切りっぱなしになっています。使い始めはほつれてきますが、通常、端から1cmほどでほつれなくなります。
赤系の地色が定番の柄
疋田文(ひったもん)
鹿の胴体にある白い斑点模様をモチーフに描かれた「鹿の子斑(かのこまだら)」文様の別名です。昔、絞り染めの絞り部分が四角形で、角が東西南北になりながら布一面に並ぶ模様は「匹田」と呼ばれました。後に「疋田」という字になりました。
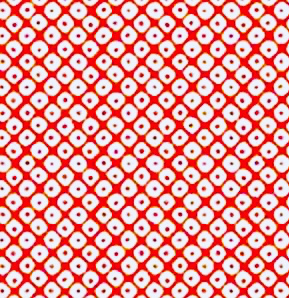
七宝つなぎ
この柄は、輪が四方八方に広がっていくことから「しっぽう」と呼ばれるようになりました。また、輪で表された人との縁は七つの宝と同じ価値があるとされ、「七宝」の漢字があてられました。
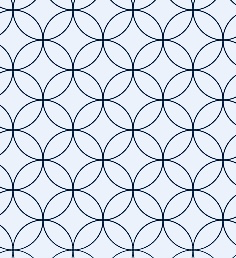
紫系の地色が定番の柄
茄子ちらし
物事を「成す」という意味があります。
緑系の地色が定番の柄
蕪(かぶ)
江戸時代、仕事場での頭領は「かぶ」と、商売で営業、専売の特権を持つ仲間は「株仲間」と呼ばれていたため、高評価の象徴とされています。
柳
柳は初春になると真っ先に芽吹くため、生命復活の象徴とされています。正月には、豊作や繁栄を願い、柳の枝に丸い餅花を付けて飾ったり、柳の木で祝箸である「柳箸」が作られていました。また、古代中国では、魔除けとして使われていました。
唐草
古典的な泥棒の風呂敷とほっかむりの柄として有名ですが、唐草の蔓は途切れなく長く続くことから「永遠に続く幸運」を象徴しています。

三益(みます)
「ますますの活躍」のように、さらなる幸運や繁栄を象徴します。

手ぬぐいの洗濯方法
手ぬぐいに使われる染料は、水に浸すと色がにじむものがあります。はじめのうちは色落ちがあるので、たっぷりの水で手洗いをしましょう。洗剤やお湯を使うと、球液に色落ちしてしまうこともあるので注意が必要です。つけ置き洗いや、濡れたまま放置することは避けましょう。色移りの可能性があるので、単独洗いがおすすめです。
濡れた手ぬぐいはすぐに陰干ししましょう。手ぬぐいは乾きが早いのも特徴です。ハワイのような気候ならば、あっという間に乾いてしまいます。
使い込むほど肌触りが柔らかく、色合いも落ち着いてきます。使い込んだ風合いは、自分になじんできた証拠。良質の手ぬぐいは、長く使うことができるのです。
なお、未使用のまま長期間放置すると、染物の場合は染料が生地に染み込みすぎて痛み、破れることがあります。すぐに使わないときは、一度洗ってからしまいましょう。
